
台湾の地上から世界に向けて短波が発信されていく。台湾の中央広播電台(台湾国際放送/RTI/Radio Taiwan International)は世界150ヶ国に向けて台湾を紹介している。台湾国際放送は激動の時代にあって、常にリスナーに寄り添い、危機を乗り越えるサポートもしてきた。
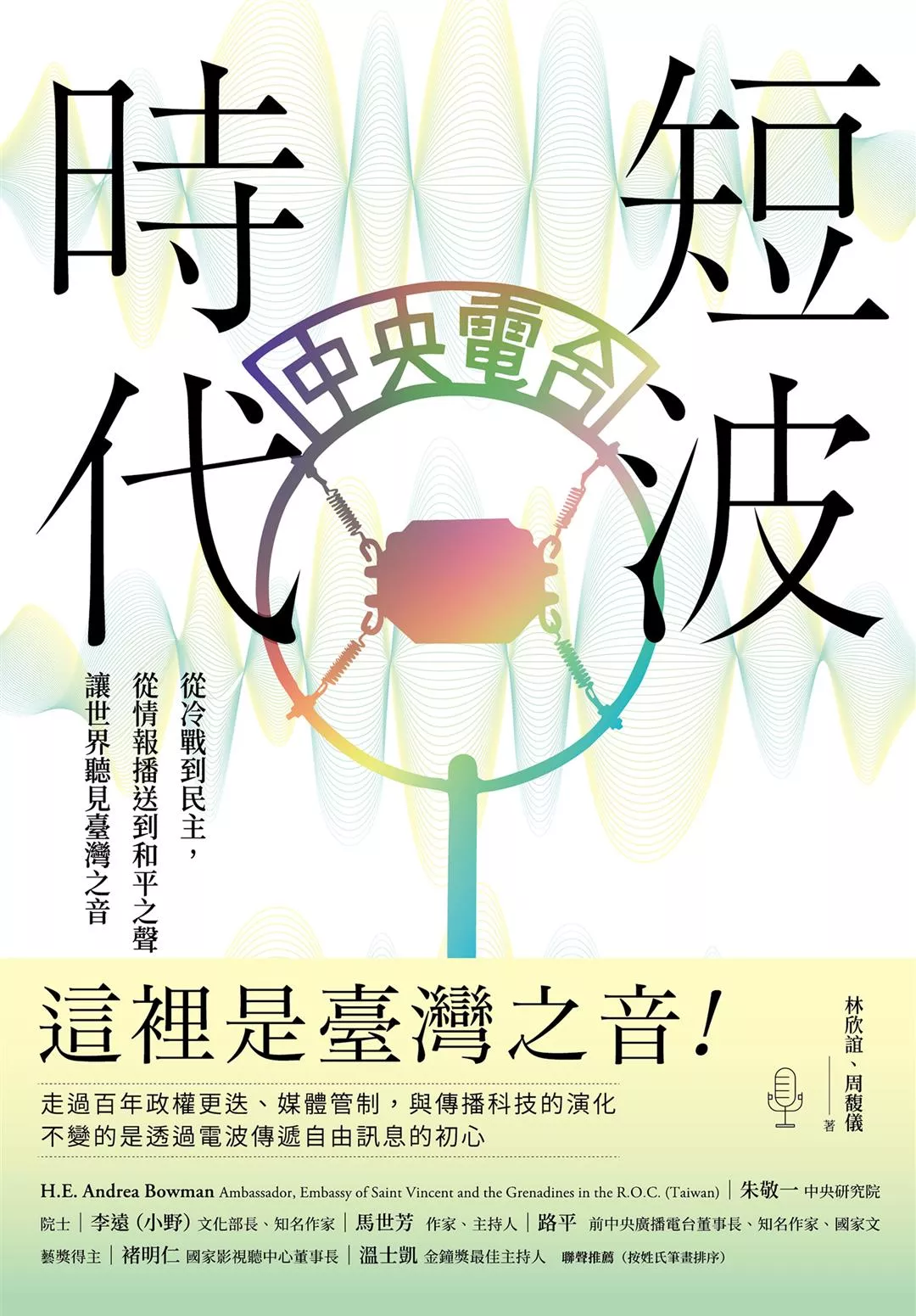
中央広播電台(RTI)が出版した『短波時代』には、台湾国際放送を通して世界に台湾を紹介する決意が書かれている。
人情味あるラジオ放送
日本の加藤夫妻は今年(2025年)の旧正月に台湾を訪れた。加藤さんにとって台湾は12回目で、来訪するたびに中央広播電台を訪れる。
50年近く台湾国際放送を聴いてきた加藤さんは2016年、番組を通して、新北市金山でシベリアへ渡る途中のツルの迷鳥が保護されたと聞き、わざわざ台湾へ来て保護の列に加わった。加藤さんはタンチョウヅルの迷鳥を2年にわたって世話した経験があったのである。
北海道在住の加藤さんは、若い頃に船で離島に働きに行った時、ネットにつながらないため短波放送を聴くようになり、それ以来、台湾国際放送日本語番組のリスナーになった。
加藤さんのように、短波を聞いていたことから台湾とつながりを持つようになったリスナーの物語は、すべて『短波時代』に収録されている。
かつて中央広播電台の台長(局長に相当)を務め、2022年に董事長に就任した頼秀和さんは、世界中のリスナーとこれほど親しく交流している放送局は、国際放送の業界でも珍しいと語る。台湾は中小規模の国で、予算は大国の比ではないが、それでも活力あるラジオ局を運営している。世界147ヶ国にリスナーがいるというのは台湾特有のソフトパワーを示している。
頼秀和さんは、英国放送協会(BBC)が以前、短波放送の聴取者数を推算した公式を使って計算する。その公式によると、リスナーから手紙が一通来たら、その背後に500人の聴取者がいるというものだ。だからこそ、台湾国際放送のパーソナリティは遠い国から送られてきた手紙の一通一通を大切にしている。

中央広播電台の頼秀和董事長によると、RTIのパーソナリティはリスナーから届く手紙を非常に大切にし、人との交流を重視している。これは国際放送業界では珍しいことで、台湾特有の「人情」と言える。(林格立撮影)
国境を越えて短波でつながる
台湾国際放送の技術者は、その日の電離層の厚みを考慮し、放送対象地域に合わせて短波の発射角度を調整している。台湾からの短波が届く最西端は、インド洋を越え、マダガスカル島東沖のレユニオン島とモーリシャス島に達する。
スペイン語番組司会者の王淑媛さんによると、スペインのリスナーが一家5人そろってラジオ局まで訪ねてきてくれたことがあり、一番下の娘さんは台湾に留学することとなり、スペイン語番組の特約スタッフを務めてくれたそうだ。
日本語番組のパーソナリティを46年にわたって続けている王淑卿さんは「台湾国際放送です」の声で親しまれ、日本のリスナーから「台湾の看板」と呼ばれている。その話によると、大阪には台湾国際放送のリスナーが自発的に結成した「玉山会」があり、1982年の創設以来、毎年集まって親睦を深めているそうだ。コロナ禍でも、オンラインでリスナーの会を12回も開いており、世界のラジオ界でも珍しいケースである。
ドイツ語番組の司会を務める邱璧輝さんの番組は、ドイツ、スイス、オーストリアのリスナーを対象としており、ベルリンとオッテナウにリスナークラブがある。ドイツ語リスナーの最大の特色は知的で理性的という点だが、中央広播電台を訪ねるために台湾旅行に来て、2時間以上もおしゃべりをしていく人もいるという。

中央広播電台が第10回第1次董監事会(取締役会)を開いた後、李遠‧文化相(右から6人目)も来訪して会談した。
台湾国際放送の素晴らしいリスナー
日本語放送のリスナー、北見隆さんと山田充郎さんは、台湾国際放送の番組を聞くようになったことがきっかけで台湾のラジオ放送について研究し始め、かつてのアングララジオのことまで熟知している。北見隆さんは『中華民国ラジオ放送簡史』も執筆しているほどだ。
南アジアには数々の短波クラブがある。台湾国際放送外国語番組編成部の黄佳山マネージャーが南アジアでリスナーの会を開こうと考えて参加者を募集したところ、バングラデシュとパキスタンでは「秒殺」で定員が埋まった。バングラデシュでは3日で150人が参加を申し込んだのである。しかし、中国からの妨害があり、リスナーの会はインドで開かれることとなった。それでも、1000キロも離れた地から2日間も列車に乗って参加してくれた人もいたのである。
50年にわたって台湾国際放送を聴取してきたインドネシアのRudy Hartonoさんは、カリマンタンのパーム農園で働いており、台湾国際放送の受信報告をフェイスブックに上げていた。最近発売された彼の著書『My Radio My Life』には、彼と台湾国際放送やNHKなどの海外の短波放送との物語が綴られている。

『短波時代』の新刊発表会には、さまざまな世代のリスナーが集まった。
「短」波が及ぼす「長」い影響
FMやAMと違い、中央広播電台は「短波(SW)」で世界に向けて台湾の声を届けている。短波放送は国境を越え、遥か彼方まで届く。
1989年6月4日、天安門広場にいた学生たちは中央広播電台の報道を聞いていた。
2011年3月11日、東日本大震災が起きた時、宮城県大崎市のリスナーは、ネットを通して中央広播電台に支援を求めてきた。
1996年、中国のミサイル試射によって台湾海峡危機が発生した時、そして1999年に台湾大地震が起きた時、台湾で働いていた外国人労働者はパニックに陥り、母国の家族からは早く帰国するよう促された。台湾で働いていたタイ出身の人々はどうすればいいのかわからなかったが、そうした中で、タイ語番組を担当する陶雲升さんが、彼らが慣れ親しんだ言語で正しい情報を提供し、在台タイ人たちを安心させたのだった。

中央広播電台では、各時代の短波ラジオと送信設備をコレクションしている。(林格立撮影)
ウクライナ語放送の開始
2022年にウクライナ戦争が始まった時、BBCはすでに停止していた短波放送を再開し、中央広播電台もウクライナのリスナーからの手紙を受け取り、ウクライナ語放送を開始した。
この戦争が始まって以降、台湾国際放送は毎日のロシア語圏向けの放送を1時間追加し、台湾がウクライナを支持していることを、ウクライナやベラルーシ、リトアニアなどのリスナーに伝え、台湾は中国とは違うことを伝えたのである。
中央広播電台は、国際放送協会(AIB)において、BBCやNHK、ドイツのドイチェ‧ヴィレ、ボイス‧オブ‧アメリカなど民主主義の盟友とのつながりを強めている。

46年にわたって日本語番組のパーソナリティを続けてきた王淑卿さん。忠実なファンにとっては、彼女の声こそ台湾の声そのものだ。(林格立撮影)
外国人労働者や新住民のために
早くも1950年代、中央広播電台は東南アジアのインドネシア、タイ、ベトナムの各言語での放送を開始し、すでに70年になる。
1990年代に入って東南アジアからの移住労働者が台湾に働きに来るようになると、東南アジア向けの短波放送の他に、中央広播電台ではAMやFMでインドネシア語、タイ語、ベトナム語の番組の放送を開始した。台湾で暮らすこれらの国々の人々のために、信頼できるニュースを伝えるだけでなく、馴染みのある母国語での放送が聞けるという安心感も届けている。
東南アジア言語のパーソナリティは、さらにリスナーからの要望に応えて生放送も開始し、移民署と協力するなどして次々と新しい番組を打ち出してきた。2024年10月にはFM104.9において新住民(東南アジアからの移住者)を主なターゲットにした「新住民心力量」という番組をスタートさせた。

ドイツ語放送パーソナリティの邱璧輝さんは、デジタルメディアでドイツ語のライブ放送を行なっており、世界中のドイツ語リスナーが聴いている。(林格立撮影)
世界中のリスナーをつなぐ
短波放送において、台湾は地理的に重要な位置にある。頼秀和さんによると、現在世界において、北朝鮮や中国、ロシア、ミャンマーなどの権威主義国家では、人々は正しい情報を得ることができない。そうした状況で短波放送はこれらの地域に届くのである。北朝鮮からの脱北者が、中央広播電台の韓国語司会者に会いに来ることも少なくないのだという。
短波放送は上空の電離層で反射して海上にも届くため、太平洋上のタンカーや遠洋漁船でも受信できる。
総台長(総局長)の張瑞昌さんは、ニューヨーク在住の韓国華僑から届いた受信報告を紹介してくれた。その日は天気が良すぎたからか、短波は北極を超えてアメリカ大陸まで届いたという報告だ。この人は、たまたまちょうど放送開始時刻に短波を聞き始め、本来は朝鮮半島向けの番組を聴取することとなったのである。
通信技術が進歩し、中央広播電台は現在、SNSやYouTubeなどでも番組を配信している。頼秀和さんによると、現在、Podcastで華語番組と英語番組を配信しているのは、若いリスナーに向けてであり、それと同時に従来の重要な短波放送においては、昔からのリスナーと新しいリスナーのニーズに応えていくという。
ネットにつないで中央広播電台を検索するか、ラジオのアンテナを伸ばしてチューニングすると、「這是台湾之音」「This is Taiwan Radio International」「これは台湾の声です」と、さまざまな言語での放送が聞こえてくる。台湾からの声が海を越えて、世界に隅々まで日々届けられているのである。

中央広播電台がリスナーに送る「受信証明書(QSL)」。台湾らしいカードで、リスナーは収集を楽しみにしている。(林格立撮影)

短波放送によってリスナー同士も強い絆で結ばれる。写真は東京の台湾国際放送リスナークラブ。

ロシア語放送再開30周年を記念して開かれたリスナーの座談会。

ドイツの台湾国際放送リスナークラブ。

インドネシア語リスナーは温かく情熱的で、リスナーの会は大いに盛り上がる。

タイ語リスナーは、中央広播電台のタイ語放送を通して台湾とのつながりを深めている。

世界の150近い国々に向けた台湾国際放送は、文化外交、メディア外交の役割を果たし、リスナーと台湾の絆を深めている。(林格立撮影)

300キロワットの短波送信機は一般のFM局の30倍という大電力で送信する。
写真は中央広播電台淡水支局の送信機。


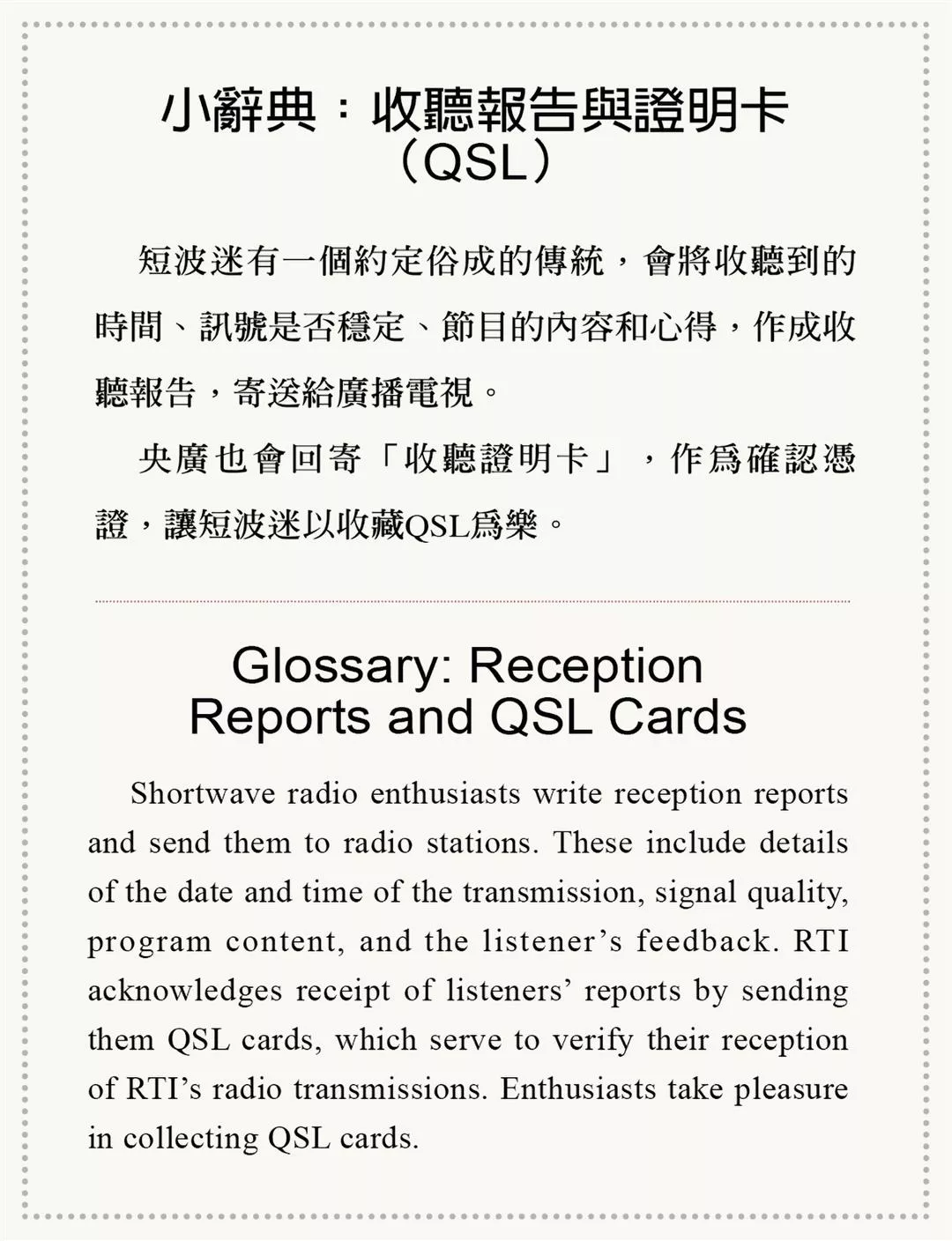


@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)




@List.jpg?w=522&h=410&mode=crop&format=webp&quality=80)